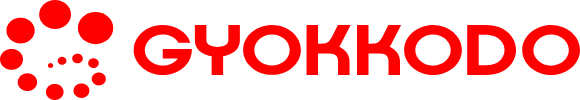2025/08/06
演歌とは?演歌が持つ3つの特徴や誕生から現在までの歴史を徹底解説

「演歌って、どんな曲?」「テレビでよく演歌を耳にするけど、ちょっと古くさいイメージがある…」そう思っていませんか?演歌は、日本の伝統的な音楽ジャンルの一つですが、その魅力は単なる「懐メロ」に留まりません。
演歌には、日本人の心の奥底にある喜怒哀楽や、人生の哀愁、そして希望が詰まっています。心に染み渡るような歌声、物語性のある歌詞、そして独特の節回しは、一度聴けば忘れられない感動を与えてくれるでしょう。
このコラムでは、演歌の基本的な特徴や歴史、そして現代にまで続くその魅力を、わかりやすく解説します。
演歌をあまり知らない方も、きっとその深遠な世界に触れることができるはずです。ぜひ最後までご覧ください。
目次
1.演歌とはどんな音楽ジャンル?
演歌とは、日本人の心の琴線に触れる独特のメロディと、こぶしと呼ばれる歌唱法、そして情念豊かな歌詞が一体となった、日本を代表するポピュラー音楽のジャンルです。
そのルーツは明治時代の演説歌にありますが、戦後の歌謡曲の中で、現在私たちが知るスタイルが確立されました。J-POPやロックとは一線を画す、その音楽的な特徴を知ると、演歌の奥深い魅力がより一層理解できます。
2.演歌を「演歌たらしめる」3つの音楽的特徴
演歌の音楽的な特徴について、以下の3つを解説します。
・感情を深く表現する独特の歌唱法「こぶし」
・日本古来の「ヨナ抜き音階」
・歌詞に頻出するキーワード
一つずつ見ていきましょう。
2-1.特徴①感情を深く表現する独特の歌唱法「こぶし」
「こぶし」とは、一つの音を、瞬間的に上下させたり、波打たせたりするように歌う、演歌の最も象徴的な歌唱テクニックです。楽譜の音符通りに歌うのではなく、母音を細かく揺らすように歌うことが特徴です。
こぶしを入れることで、歌詞に込められた喜びや悲しみ、未練といった感情を、より深くそしてドラマチックに表現することができます。
2-2.特徴②日本古来の「ヨナ抜き音階(ペンタトニックスケール)」
多くの演歌のメロディは、「ヨナ抜き音階」と呼ばれる、日本古来の音階にもとづいて作られています。ヨナ抜き音階とは、西洋音楽の「ドレミファソラシ」の7音から、4番目の「ファ」と7番目の「シ」を抜いた、「ドレミソラ」の5音で構成される音階です。この音階を使うと、どこか懐かしく、日本人の心に自然と馴染む、独特の哀愁を帯びたメロディが生まれます。
私たちが演歌を聴いて「日本らしい」と感じるのは、このヨナ抜き音階が大きく影響しています。
2-3.特徴③歌詞に頻出するキーワード(港、酒、雪、別れ、故郷など)
演歌の歌詞には、繰り返し登場する以下のような象徴的なキーワードが存在します。
・港
・酒
・雪
・涙
・雨
・別れ
・故郷
これらのキーワードは、単なる言葉としてだけでなく、聴く人が自らの人生経験や感情を重ね合わせるための、「舞台装置」のような役割を果たしています。
たとえば、「港」は出会いと別れの場、「酒」は悲しみを紛らわす友、といった具合です。これらのキーワードが、聴く人それぞれの心象風景を呼び起こし、歌の世界への深い共感を生み出します。
3.演歌の歴史:誕生から現在に至るまで
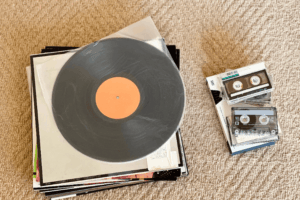
ここからは、演歌にはどのような歴史があるのか、誕生から現在に至るまで詳しく解説していきます。演歌がどのように生まれ、そして変化していったのかを、時代を追って詳しく見ていきましょう。
3-1.演歌誕生の流れ
まずは、演歌誕生の流れを3つの大きな要素に分けて、順を追って解説していきます。
3-1-1.明治時代の「演説歌」が起源
演歌の最も古い起源は、明治時代の自由民権運動家たちが、政府の言論弾圧に対抗するために生み出した「演説歌(えんぜつか)」です。
演説会が禁止されるなかで、彼らは自らの政治的主張や風刺を、覚えやすいメロディに乗せて街頭で歌いました。これが、演説の代わりに歌う「演歌」の始まりです。「演歌」は、「演説歌」の略称であることがわかります。
当初の演歌は、恋愛や人情ではなく、社会へのメッセージを伝えるための、力強いプロパガンダソングでした。
3-1-2.「田舎調」の流行
政治の季節が過ぎた大正時代には、演歌師たちが歌う歌の内容が、望郷の念や、都会での暮らしの悲哀を歌う「田舎節(いなかぶし)」へと変化し、流行しました。都会に出てきた地方出身者たちの心を慰める、感傷的なメロディと歌詞が、多くの人々の共感を呼んだのです。
バイオリンの伴奏で歌われることも多く、これが現代の演歌が持つ、哀愁を帯びた雰囲気の原型となりました。この時期に、演歌は政治の歌から、個人の心情を歌う音楽へと、その性質を大きく変えました。
3-1-3.演歌の知名度向上
演歌の知名度が全国的に向上したのは、大正から昭和初期にかけて、レコードとラジオという新しいメディアが普及したことが大きなきっかけです。
これまで街頭でしか聴けなかった演歌師の歌が、レコードに記録され、ラジオ放送で全国の家庭に届けられるようになりました。これにより、演歌は一部の人が聴く音楽から、日本中の誰もが楽しめる、大衆的な音楽ジャンルへと成長したのです。
メディアの発達が、演歌を国民的な音楽へと押し上げる原動力となりました。
3-2.演歌誕生後の変遷
レコード歌謡として定着した演歌は、戦後の昭和時代に黄金期を迎え、その後、J-POPの台頭による変化を経ながら、現代へと継承されています。
演歌誕生後の変遷について、詳しく見ていきましょう。
3-2-1.昭和(戦後):歌謡曲の主流となり黄金時代を迎える
戦後の昭和時代、演歌は「歌謡曲」の主流として、その黄金期を築き上げます。
作曲家の古賀政男などが作り上げた日本的なメロディ(古賀メロディー)と、こぶしを効かせた歌唱法がこの時期に確立されました。美空ひばりといった国民的スターが登場し、テレビを通じて、演歌はお茶の間の中心的なエンターテインメントとなったのです。
現在私たちが「演歌」としてイメージする、音楽スタイルと世界観が完成した時代でした。
3-2-2.平成:J-POPの台頭と、演歌の多様化
1990年代以降の平成時代は、J-POPが音楽市場の主役となり、演歌がその立ち位置を大きく変えた、多様化の時代です。演歌は、主に中高年層が愛聴する、安定したジャンルへと変化しました。
そのなかで、氷川きよしのような若いスターが登場し、新たなファンを獲得したり、演歌歌手がポップスを歌ったりと、ジャンルの枠組みを広げる試みも多く見られました。メインストリームから一歩引いたことで、より深く、その様式美が追求された時代ともいえます。
3-2-3.現代:日本の伝統音楽としての継承と再評価
現代における演歌は、日本の音楽文化を象徴する「伝統音楽」の一つとして継承され、そして国内外から再評価されています。カラオケの定番ジャンルとして、世代を超えて歌い継がれています。
また近年では、その独特の節回しや感情表現が、海外の日本文化ファンから「エモーショナルだ」として、新たな注目を集めているのです。演歌は、単なる古い音楽ではなく、今もなお、日本の心を伝える文化として生き続けています。
4.演歌を代表する有名歌手
演歌の世界を深く知るには、その歴史を築き上げ、象徴する存在となった、伝説的な歌手たちの歌声に触れるのが一番です。ここでは、数多くの名歌手の中から、とくに演歌の歴史を語るうえで欠かせない以下の3人をご紹介します。
・美空ひばり
・北島三郎
・石川さゆり
それぞれ見ていきましょう。
4-1.演歌の女王「美空ひばり」
美空ひばりさんは、その圧倒的な歌唱力と表現力で、戦後の日本国民に夢と希望を与え、「演歌の女王」として今なお絶大な尊敬を集める、不世出の歌手です。「川の流れのように」や「愛燦燦」といった名曲は、ジャンルや世代を超えて、全ての日本人の心に響く普遍的な力を持っています。
彼女の歌声そのものが、昭和という時代の象徴であり、演歌というジャンルの格式を決定づけたといっても過言ではありません。
4-2.演歌界の重鎮「北島三郎」
北島三郎さんは、その力強く、男らしい歌声で、数多くのヒット曲を世に送り出し、長年にわたって演歌界のトップに君臨し続ける「重鎮」です。「まつり」や「与作」といった楽曲は、日本の祭りや風土と結びつき、国民的な歌として親しまれています。
また、紅白歌合戦での大トリを何度も務めるなど、その存在感は演歌界の象徴といえます。豪快で義理人情に厚い、偉大な演歌歌手です。
4-3.時代を超えて愛される「石川さゆり」
石川さゆりさんは、名曲「津軽海峡・冬景色」や「天城越え」で知られ、デビューから現在まで、第一線で活躍し続ける、時代を超えて愛される国民的歌手です。
伝統的な演歌の様式美を完璧に表現する高い歌唱力を持ちながら、ポップスやロックのアーティストとも積極的に共演するなど、常に新しい挑戦を続けています。その姿勢が、演歌の魅力を新しい世代にも伝え、ファン層を広げています。
まさに、伝統と革新を両立させ、演歌の可能性を広げ続ける存在といえるでしょう。
5.演歌と海外との繋がり
演歌は、日本国内だけでなく、とくに「台湾」や「韓国」などの国々で、その国のポピュラー音楽に大きな影響を与え、独自の形で受容されてきました。日本の統治時代や戦後の文化交流を通じて、演歌のメロディや歌唱法が海を渡り、現地の音楽と融合したのです。
それぞれ解説します。
5-1.台湾における演歌
台湾では、日本の演歌が現地の言葉である台湾語の歌詞でカバーされ、「台語流行音樂(台湾語ポップス)」というジャンルの発展に、非常に大きな影響を与えました。
日本統治時代から戦後にかけて、多くの日本の演歌・歌謡曲が台湾に伝わり、現地の歌手によってカバーされました。そのメロディは、今なお、年配層を中心にカラオケなどで広く親しまれています。
台湾のポピュラー音楽のルーツを辿ると、日本の演歌に行き着くケースは少なくありません。
5-2.韓国における演歌
韓国の大衆音楽である「トロット(Trot)」は、日本の演歌と音楽的なルーツを共有しており、非常によく似た特徴を持つジャンルです。日本統治時代に日本の歌謡曲の影響を受けて生まれたとされ、演歌と同じように、独特の節回し(こぶし)や、哀愁を帯びたメロディが特徴です。
近年、韓国では若者の間でトロットブームが再燃しています。演歌とトロットは、互いに影響を与え合った、いわば兄弟のような関係の音楽といえるでしょう。
6.演歌とJ-POP・歌謡曲との違い

演歌とJ-POP、そして歌謡曲は、いずれも「邦楽」ですが、その音楽的な特徴や生まれた時代背景によって、区別することができます。これらの違いを理解すると、日本のポピュラー音楽の歴史の大きな流れが見えてくるでしょう。
ここでは、それぞれの違いを分かりやすく解説します。
6-1.演歌とJ-POPの違い
演歌とJ-POPの最も大きな違いは、演歌が「歌い手のこぶしや感情表現」を重視するのに対し、J-POPは「リズムやビート感」を重視する点にあります。
演歌は、日本語の歌詞を聴かせることを主眼とした、メロディ中心の音楽です。一方、J-POPは、洋楽のポップスやロックの影響を強く受けており、踊れるようなリズミカルな楽曲が多く、歌詞に英語が混じることも頻繁です。
関連記事:邦楽とJ-POPの違いとは?それぞれの言葉の意味やアーティスト例
6-2.演歌と歌謡曲の違い
演歌と歌謡曲の違いは非常に曖昧で、明確な境界線を引くのが難しいですが、一般的には「歌謡曲」という大きな枠のなかに、「演歌」という一つのスタイルが含まれる、と理解されています。
「歌謡曲」は、戦後の日本のポピュラー音楽全般を指す広い言葉です。そのなかでも、とくに日本的な情緒やこぶしといった伝統的な歌唱法を色濃く反映したものが「演歌」と呼ばれている、と考えると分かりやすいです。
関連記事:歌謡曲とは?歌謡曲の歴史や時代背景・演歌やJ-POPなどとの違い
7.まとめ
演歌は、日本の伝統的な歌唱法や音階をベースに、日本人の心の機微を表現してきた独自の音楽文化です。その歴史は古く、明治時代から人々の喜怒哀楽に寄り添い、時代を超えて歌い継がれてきました。物語性のある歌詞や、こぶしを利かせた独特の歌い方は、演歌の大きな魅力です。
現代では若手アーティストも登場し、新しいファン層を獲得しています。演歌は決して過去の音楽ではなく、私たちの感情に深く響く普遍的なテーマを持っているのです。
本コラムを通して、演歌に少しでも興味を持っていただけたなら幸いです。ぜひ、お気に入りの一曲を見つけて、その奥深い世界を体験してみてください。
GYOKKODOでは、CDやDVD、レコード、ギターなど、音楽関連商品の高価買取を実施中です。ご自宅に不要になったCD・DVD・レコードがある方は、GYOKKODOの店頭買取や宅配買取をぜひご利用ください。
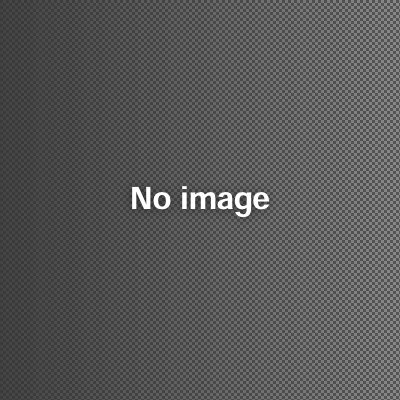
コラム監修者
テキスト〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇