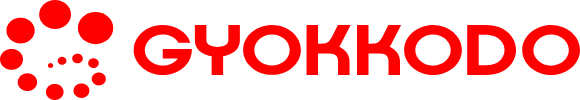2025/08/06
歌謡曲とは?歌謡曲の歴史や時代背景・演歌やJ-POPなどとの違い

「歌謡曲って、どんな音楽のことだろう?」「演歌やポップスとどう違うの?」そう疑問に思ったことはありませんか?歌謡曲は、私たちの親世代や祖父母世代が聴いてきた、日本の大衆音楽の大きな柱です。
しかし、その定義は意外と曖昧で、一言で説明するのは難しいかもしれません。このコラムでは、歌謡曲が持つ独特の魅力や、時代とともに変化してきたその歴史をわかりやすく解説します。
演歌やJ-POPとの違いを明確にしながら、歌謡曲がなぜ多くの人々に愛されてきたのか、その理由を探っていきましょう。この記事を読めば、歌謡曲の奥深い世界に一歩踏み込めるはずです。
目次
1.歌謡曲とは?
歌謡曲は、日本独自のメロディと西洋音楽が融合したポピュラー音楽の総称です。幅広い世代に親しまれるよう、時代ごとに多様な音楽性を取り入れてきました。
歌詞は恋愛や人生、季節の風景など、人々の日常に寄り添うテーマが多くなっています。また、時代ごとの流行を色濃く反映し、常に変化し続けてきた点が大きな特徴です。
歌謡曲は、時代を映す鏡として日本の音楽文化を形成してきました。
2.歌謡曲の歴史と時代背景

歌謡曲の歴史と時代背景を、以下にまとめました。
・歌謡曲の黎明期(明治~昭和初期)
・テレビの普及とグループサウンズの時代(1950~60年代)
・フォーク・ニューミュージックの台頭とアイドル全盛期の時代(1970~80年代)
・J-POPへの移行と歌謡曲の変容(1980年代後半~)
順を追って解説します。
2-1.歌謡曲の黎明期(明治~昭和初期)
歌謡曲の原型は、西洋音楽と日本の伝統音階が融合した「流行歌」です。明治時代に西洋から音楽理論や楽器が伝わり、新しい大衆音楽が生まれました。
中山晋平らが作曲した楽曲は、日本的な旋律に洋楽の要素を取り入れています。そして、レコードの普及は、音楽を大衆が家庭で楽しむ文化へと変化し、日本のポピュラー音楽の礎が築かれました。
2-2.テレビの普及とグループサウンズの時代(1950~60年代)
テレビの普及は、歌謡曲を国民的エンターテイメントに押し上げました。映像を通じてスターの魅力が、直接お茶の間に届けられるようになった時代です。
とくに美空ひばりや坂本九などのスターが、テレビ番組から数々のヒット曲を生み出しています。当時の若者の間では、エレキギターを中心としたグループサウンズが熱狂的なブームになりました。
テレビという新しいメディアが、歌謡曲の黄金時代を築く原動力となったのです。
2-3.フォーク・ニューミュージックの台頭とアイドル全盛期の時代(1970~80年代)
1970年代、歌謡曲はフォークやニューミュージックの登場で大きく多様化していきます。アーティストが自ら作詞作曲し、社会的なメッセージを歌うフォークソングが若者の心を捉えました。
また、都会的で洗練されたニューミュージックも、新しい音楽シーンを形成していきます。そして、テレビのオーディション番組から、国民的アイドルが次々と誕生しました。
さまざまな才能が開花し、歌謡曲の表現の幅が大きく広がった時代です。
2-4.J-POPへの移行と歌謡曲の変容(1980年代後半~)
1980年代後半は、「歌謡曲」から「J-POP」への移行が進んだ変革期です。主にシンセサイザーや打ち込みといった電子楽器が、サウンドに大きな変化をもたらしました。また、BOØWYに代表されるバンドブームが到来し、ロックが大衆に広がっています。
さらに、アーティスト自身が楽曲制作から表現までを手掛けるスタイルが主流になりました。各要素が融合したことで、現代の日本のポップミュージックの原型が完成したのです。
3.歌謡曲と他ジャンル(演歌・J-POP)との違いは?
歌謡曲と他ジャンルとの違いを、以下にまとめました。
・演歌との違い
・J-POPとの違い
・フォーク・ニューミュージックとの関係
ひとつずつ解説します。
3-1.演歌との違い
歌謡曲と演歌の大きな違いは、音楽的な表現の幅広さです。演歌は「こぶし」と呼ばれる独特の節回しで、情念や哀愁を力強く歌い上げます。また、歌詞のテーマも、義理人情や未練、望郷といった内容が多く見られます。
一方、歌謡曲はポップスやロック、ラテンなど多様な音楽ジャンルの要素を取り入れています。愛や青春、社会風刺まで、より多彩なテーマを扱ってきた点が特徴です。
関連記事:演歌とは?演歌が持つ3つの特徴や誕生から現在までの歴史を徹底解説
3-2.J-POPとの違い
歌謡曲とJ-POPは、楽曲の構成と制作スタイルに違いがあります。歌謡曲は、覚えやすく口ずさみやすいメロディラインを最も重視する傾向があります。主に作詞家や作曲家、編曲家や歌手などによる分業体制が基本でした。
対してJ-POPは、洋楽の影響を強く受けたビートやリズムが楽曲の中心です。アーティスト自身が作詞作曲を手掛けるシンガーソングライターが主流を占めています。メロディとリズムのどちらを主軸に置くかと制作過程が、両者を区別する重要な要素です。
関連記事:邦楽とJ-POPの違いとは?それぞれの言葉の意味やアーティスト例
3-1.フォーク・ニューミュージックとの関係
フォークやニューミュージックは、歌謡曲と相互に影響を与え合った関係です。当初、フォークは商業的な歌謡曲へのカウンターとして生まれました。井上陽水や吉田拓郎らの楽曲がヒットし、歌謡界に大きな影響を与えました。
また、荒井由実(松任谷由実)らのニューミュージックは、歌謡曲に都会的な洗練さをもたらしています。各ジャンルが融合したことで、後のJ-POPへとつながる土壌を形成しました。
4.【年代別】歌謡曲の代表的なアーティスト

年代別に歌謡曲を、以下にまとめました。
・【1950~60年代】戦後復興を象徴する大スターとGSブームの名曲
・【1970年代】テレビから生まれたアイドルとフォーク・ニューミュージックの名曲
・【1980年代】アイドル黄金期とシティポップの誕生を彩った名曲
ひとつずつ解説します。
4-1.【1950~60年代】戦後復興を象徴する大スターとGSブームの名曲
1950〜60年代の戦後復興を象徴する大スターとGSブームの名曲は、以下のとおりです。
・時代を象徴する不世出の歌姫・美空ひばり
・国民的ヒットを生んだスターたち(坂本九・加山雄三ほか)
・歌謡界を席巻した御三家(橋幸夫・舟木一夫・西郷輝彦)
・若者を熱狂させたグループサウンズ(GS)ブーム
それぞれ解説します。
4-1-1.時代を象徴する不世出の歌姫・美空ひばり
美空ひばりは、戦後の日本を象徴する不世出の歌姫です。幼い頃から天才少女と呼ばれ、数多くの国民的ヒット曲を世に送り出しました。
たとえば「悲しき口笛」や「川の流れのように」など、卓越した歌声は多くの国民を勇気づけています。ジャズやブルースなど幅広いジャンルを歌いこなし、歌謡曲の表現を大きく広げました。
美空ひばりの存在が、戦後歌謡史の輝かしい一時代を築いています。
4-1-2.民的ヒットを生んだスターたち(坂本九・加山雄三ほか)
1950〜60年代、国民的な人気を博す男性スターが次々と登場していきます。たとえば、坂本九の「上を向いて歩こう」は、全米チャート1位を獲得する歴史的快挙を成し遂げました。
また、加山雄三は、自ら作詞作曲を手掛ける若大将シリーズで絶大な人気を得ています。
スターたちの明るく希望に満ちた歌は、高度経済成長期の日本を象徴するものでした。テレビを通じて、坂本九や加山雄三の音楽は世代を超えて愛される国民的ソングとなったのです。
4-1-3.歌謡界を席巻した御三家(橋幸夫・舟木一夫・西郷輝彦)
橋幸夫、舟木一夫、西郷輝彦の三人は「御三家」として歌謡界を席巻しました。それぞれが持つ個性的な魅力で、多くの女性ファンの心を掴みました。
橋幸夫はリズム歌謡、舟木一夫は青春歌謡、西郷輝彦は男らしい魅力で一時代を築きました。この「御三家」の活躍は、のちのアイドル像の原型を作ったとされています。三人三様のスター性が、1960年代の歌謡界を大いに盛り上げました。
4-1-4.若者を熱狂させたグループサウンズ(GS)ブーム
1960年代後半は、グループサウンズ(GS)が若者文化の中心となった時代です。たとえば、ザ・タイガースやザ・スパイダースなどが、若者の熱狂的な支持を集めました。
エレキギターをかき鳴らし、長髪を揺らすスタイルは社会現象になりました。ビートルズなど海外のロックバンドから強い影響を受けています。
GSブームは、日本のポピュラー音楽にロックの要素を定着させる大きなきっかけとなりました。
4-2.【1970年代】テレビから生まれたアイドルとフォーク・ニューミュージックの名曲
1970年代にテレビから生まれたアイドルとフォーク・ニューミュージックの名曲は、以下のとおりです。
・オーディション番組から誕生したアイドル歌謡(山口百恵・ピンク・レディーほか)
・社会現象となったフォークソングブーム(よしだたくろう・かぐや姫ほか)
・洗練されたサウンドで時代をリードしたニューミュージック(荒井由実ほか)
ひとつずつ解説します。
4-2-1.オーディション番組から誕生したアイドル歌謡(山口百恵・ピンク・レディーほか)
1970年代は、テレビのオーディション番組から新しいスターが誕生した時代です。そのなかでも、伝説の番組である「スター誕生!」からは、山口百恵やピンク・レディーがデビューしはじめます。
山口百恵は、深い陰影を帯びた楽曲で絶大な人気を博しました。また、ピンク・レディーは、キャッチーな楽曲と斬新な振り付けで社会現象を巻き起こしています。
テレビから生まれたアイドルが、70年代の歌謡シーンを華やかに彩った時代です。
4-2-2.社会現象となったフォークソングブーム(吉田拓郎・かぐや姫ほか)
1970年代、フォークソングは若者の心情を代弁する音楽として社会現象になります。吉田拓郎は、既存の歌謡曲の常識を覆すスタイルでカリスマとなりました。
また、かぐや姫の「神田川」は、同棲というテーマを歌い大ヒットを記録しています。若者たちは自らの思いを重ね、フォークソングを熱心に支持しました。フォークソングブームは、シンガーソングライターという存在を日本の音楽シーンに確立させました。
4-2-3.洗練されたサウンドで時代をリードしたニューミュージック(荒井由実ほか)
ニューミュージックは、洗練された都会的なサウンドで時代をリードしました。
とくに、荒井由実(松任谷由実)は、卓越したメロディセンスと情景が浮かぶ歌詞でシーンを牽引しています。荒井由実の楽曲は、従来の歌謡曲にはない新しい感性を持っていました。そのほか、オフコースやチューリップなども、美しいハーモニーとサウンドで当時の人気を博しています。
ニューミュージックの登場は、歌謡曲の音楽的な質を大きく向上させました。
4-3.【1980年代】アイドル黄金期とシティポップの誕生を彩った名曲
1980年代のアイドル黄金期とシティポップの誕生を彩った名曲は、以下のとおりです。
・多彩なタレントが咲き誇ったアイドル黄金期(松田聖子・中森明菜ほか)
・バブル景気を背景に流行したシティポップ(山下達郎・竹内まりやほか)
・J-POPの礎を築いたバンドブームの到来(BOØWY・レベッカほか)
それぞれ解説します。
4-3-1.多彩なタレントが咲き誇ったアイドル黄金期(松田聖子・中森明菜ほか)
1980年代は、まさにアイドル黄金期と呼べる時代でした。
とくに、松田聖子は圧倒的なスター性と歌声でトップアイドルの座に君臨します。また、中森明菜は、卓越した歌唱力と陰りのある表現で独自の路線を築きました。さらに、おニャン子クラブなど、数多くのアイドルがテレビを舞台に活躍しはじめます。
アイドルたちの存在が、80年代の文化そのものを形作っていた時代です。
4-3-2.バブル景気を背景に流行したシティポップ(山下達郎・竹内まりやほか)
シティポップは、バブル景気の高揚感を背景に生まれた都会的な音楽です。山下達郎や竹内まりやは、洗練されたサウンドでジャンルを代表する存在となりました。
大滝詠一のアルバム「A LONG VACATION」は、シティポップの金字塔として知られています。ドライブやリゾートといった、豊かなライフスタイルを音楽で表現しました。
80年代のサウンドは、近年海外でも高く評価されています。
4-3-3.J-POPの礎を築いたバンドブームの到来(BOØWY・レベッカほか)
1980年代後半、日本の音楽シーンはバンドブームに沸きました。ライブハウスから生まれたバンドが、次々とヒットチャートを席巻しています。
たとえば、BOØWYは、カリスマ性と革新的なサウンドでロックシーンの頂点に立っています。またレベッカは、NOKKOのパワフルなボーカルでミリオンセラーを記録しました。
バンドブームの大きなうねりが、後のJ-POP時代へと直接つながっていきました。
5.歌謡曲から派生した音楽ジャンル
歌謡曲と他ジャンルとの違いを、以下にまとめました。
・世界的な再評価が進むシティポップ
・独自の進化を遂げたアニメソング
・歌謡曲を土台に発展した現代のJ-POP
ひとつずつ解説します。
5-1.世界的な再評価が進むシティポップ
シティポップは、歌謡曲から派生し世界で再評価されているジャンルです。1980年代の日本の楽曲が、動画サイトなどを通じて海外の若者に発見されました。
たとえば、竹内まりやの「プラスティック・ラブ」が、ブームの火付け役となります。洗練されたメロディと演奏技術の高さが、新鮮な驚きをもって受け入れられました。
シティポップによって、日本の歌謡曲が持つ普遍的な魅力が時代と国境を超えて証明されたのです。
5-2.独自の進化を遂げたアニメソング
アニメソングは、歌謡曲をルーツに持ちながら独自の進化を遂げました。初期のアニメ主題歌は、有名な歌謡曲の歌手や作家が手掛けることが多かったです。
やがて、作品の世界観と深く結びついた楽曲が作られるようになっていきます。現在では、人気アーティストが楽曲を提供することも珍しくありません。
アニメソングは、今や世界に誇る日本のポップカルチャーを代表する音楽ジャンルです。
5-3.歌謡曲を土台に発展した現代のJ-POP
現代のJ-POPは、歌謡曲という大きな土台の上に成り立っています。一見すると音楽性は大きく異なりますが、根底には共通点があります。
多くのJ-POPにみられる、キャッチーで覚えやすいサビのメロディは代表的な例です。日本人の琴線に触れる歌詞の表現方法にも、歌謡曲から続く伝統が見られています。
6.まとめ
歌謡曲は、日本独自のメロディと西洋音楽が融合したポピュラー音楽の総称です。歌詞は恋愛や人生、季節の風景など、人々の日常に寄り添うテーマを扱っています。
もし、この記事をきっかけに音楽への情熱が再燃し、レコードやギター、CDの整理をお考えなら、玉光堂の買取サービスがおすすめです。
GYOKKODOでは、CDやDVD、レコード、ギターなど、音楽関連商品の高価買取を実施中です。ご自宅に不要になったCD・DVD・レコードがある方は、GYOKKODOの店頭買取や宅配買取をぜひご利用ください。
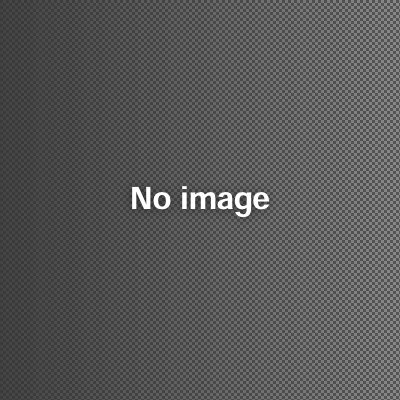
コラム監修者
テキスト〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇