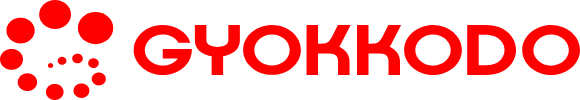2025/08/12
レコードの大きさは3種類!サイズによる回転数・収録時間の違い

近年人気が再燃しているアナログレコード。その温かみのあるサウンドや、大きなジャケットアートに魅力を感じ、レコードを手にした方も多いのではないでしょうか。
しかし、いざレコード店に足を運ぶと、LP盤や7インチ盤など、大きさや形が違うレコードがあり、どれが何なのか迷ってしまいます。
そこでこの記事では、そんなレコード初心者のあなたのために、レコードの大きさや回転数の違いといった基本から、正しい再生・保管方法までを徹底解説します。
レコードを購入する際に役立つ情報満載ですので、レコードを買ってみたいと思っている方は、ぜひ最後までご覧ください。
目次
1.レコードの大きさは主に3種類!

アナログレコードの大きさは、主に以下の3種類に分けられます。
・12インチ盤(LP盤)
・7インチ盤(EP盤/ドーナツ盤)
・10インチ盤
ここでは、それぞれの規格について、その呼び名や特徴を詳しく見ていきましょう。
1-1.①12インチ盤(LP盤):アルバム作品で最も一般的
直径約30cmの12インチ盤は、長時間再生できることから「LP盤(Long Play)」とも呼ばれ、アルバム作品を収録する際に最も一般的に使われる、レコードの標準サイズです。
毎分33 1/3回転(33rpm)で再生し、片面に20分〜30分程度の音楽を収録できます。そのため、アーティストのアルバム作品は、そのほとんどがこのLP盤でリリースされています。
レコードといえば多くの人がこのサイズを思い浮かべる、まさに王道といえる規格です。
1-2.②7インチ盤(EP盤/ドーナツ盤):シングル曲の定番
直径約18cmの7インチ盤は、片面に1〜2曲を収録する「シングル盤」として使われる、コンパクトなレコードです。
中心部の穴が大きい見た目から、「ドーナツ盤」という愛称で親しまれています。また、収録時間がLPよりは長く、シングルよりは少し長いことから「EP盤(Extended Play)」とも呼ばれます。再生速度は、毎分45回転(45rpm)が基本です。
このレコードを再生するには、中央の大きな穴を埋めるための「EPアダプター」が必要になるので、覚えておきましょう。
関連記事:「EP」の意味とは?定義やシングル・アルバムとの違いについて
1-3.③10インチ盤:LPとEPの中間サイズ
直径約25cmの10インチ盤は、LP盤とEP盤の中間にあたる、比較的見かける機会の少ない特殊なサイズのレコードです。LP盤が登場する以前のSP盤時代には主流でしたが、LP盤の登場以降は、生産数が少なくなりました。
現代では、数曲入りのミニアルバムや、限定盤、復刻盤といった、特別な作品で採用されることがあります。回転数も33回転、45回転、78回転と、作品によって様々です。もし中古レコード店などで見かけたら、少し珍しい規格のレコードといえるでしょう。
2.レコードの大きさと収録時間・音質の関係
レコードは、その物理的な大きさが、収録できる時間と再生される音質に直接的な関係を持っています。
レコードは、溝の長さに比例して収録時間が決まるため、盤のサイズが大きければ大きいほど、より長い時間、音楽を記録できるのです。また、盤の大きさが大きいほど、溝の間隔を広く刻めるため、よりダイナミックで豊かな音質を実現することが可能です。これが、アルバム(LP)には大きな12インチ盤が、シングル曲には小さな7インチ盤が主に使われる理由です。
このように、レコードの大きさは、単なる見た目ではなく、その中身である音楽体験そのものを規定する重要な要素といえます。
関連記事:レコードから音が出る仕組みをわかりやすく解説 | 溝や針と音の関係
3.【大きさだけじゃない】回転数(RPM)と収録時間によるレコードの違い
レコードの種類を決定するもう一つの重要な要素が、1分間に何回転するかを示す「回転数(RPM)」です。
回転数が速いほど、同じ時間でより多くの溝が針の下を通過するため、音質は高くなりますが、収録時間は短くなります。逆に、回転数が遅いと、収録時間は長くなりますが、音質は相対的に劣る傾向があります。
3-1.3種類の回転数(33回転・45回転・78回転)
レコードの回転数は、主にLP盤で使われる「33回転(33 1/3rpm)」、シングル盤で使われる「45回転(45rpm)」、そして古いSP盤の「78回転(78rpm)」の3種類です。
33回転は、長い収録時間を確保できるためアルバム向きです。45回転は、収録時間は短いものの、溝の幅を広く取れるため、よりパワフルで高音質なサウンドを実現でき、とくにダンスミュージックのシングルなどで好まれます。78回転は、非常に古い規格であり、再生するには専用の針やプレーヤーが必要となります。
お手持ちのレコードを再生する前には、必ず盤面に記載された正しい回転数を確認しましょう。
4.レコードの大きさに合わせた正しい再生方法
レコードを正しく再生するためには、盤の規格に合わせて、レコードプレーヤーの「回転数」を切り替え、必要に応じて「EPアダプター」を使用することが基本となります。これらの設定を間違えてしまうと、音楽が本来の速さや音程で再生されないだけでなく、レコードや針を傷める原因にもなりかねません。
レコードの正しい再生方法をマスターして、より良い音で楽しみましょう。
4-1.レコードプレーヤーの回転数を正しく設定しよう
レコードを再生する前には、その盤に合った回転数(33回転または45回転)に、プレーヤーのスイッチを正しく設定してください。もし設定を間違えると、音楽の速さと音程が大きく変わってしまいます。
45回転のレコードを33回転で再生すれば、スローで低い音になり、逆に33回転のレコードを45回転で再生すると、早回しで甲高い音になってしまいます。
多くのプレーヤーには「33」と「45」を切り替えるスイッチやボタンが付いています。LP盤なら33、7インチ盤なら45に合わせるのが基本です。
4-2.7インチ盤(ドーナツ盤)に必要なEPアダプター
中心の穴が大きい7インチ盤(ドーナツ盤)を再生するには、その穴を埋めてプレーヤーの中心軸(スピンドル)に固定するための「EPアダプター」という部品が必要です。このアダプターがないと、レコードが回転の中心からずれてしまい、正常に再生できません。
EPアダプターは、通常レコードプレーヤーに付属していることが多いですが、無い場合は数百円程度で購入可能です。
使い方は簡単で、まずプレーヤーの中心軸にEPアダプターをはめ込み、その上から7インチ盤を置くだけです。これで、ドーナツ盤も他のレコードと同じように楽しむことができます。
5.レコードは素材による違いもある
レコードは、素材によって耐久性や重さ、そして再生時に必要な針の種類が異なります。
・塩化ビニール製(ヴァイナル)
・シェラック製
・ソノシート
とくに古いレコードを扱う際には、その素材を理解しておくことが、レコードと再生機器の両方を守る上で非常に重要です。
5-1.塩化ビニール製(ヴァイナル)
塩化ビニール(ポリ塩化ビニル)は、現在私たちが「レコード」として最も一般的に接している、LP盤やEP盤に使われている素材です。「ヴァイナル」とも呼ばれ、後述するシェラック製のSP盤に比べて、格段に割れにくく、ノイズが少ないという優れた特徴を持っています。
塩化ビニールの登場が、長時間収録が可能なLP盤の普及を大きく後押ししました。私たちが普段レコードプレーヤーで聴いている音楽のほとんどは、この塩化ビニール製のレコードです。
5-2.シェラック製
シェラックとは、カイガラムシという虫の分泌物から作られる天然樹脂で、LP盤が普及する以前の「SP盤」の主原料として使われていた素材です。塩化ビニールに比べて非常にもろく、落としただけで簡単に割れてしまうのが大きな特徴です。
また、再生にはLP用の針とは先端の形状が違う、太い「SP盤専用の針」が必要となります。もし間違った針で再生すると、レコードの溝を激しく損傷させてしまうため、注意しなければなりません。
5-3.ソノシート
ソノシートは、塩化ビニールなどで作られた、非常に薄く、手で曲げられるほど柔らかいシート状のレコードです。「フォノシート」や「フレキシディスク」とも呼ばれます。
安価に大量生産できるため、1960年代から80年代にかけて、雑誌の付録や、プロモーション用の景品として広く配布されました。音質は通常のレコードに劣り、耐久性も低いのが特徴です。
当時の人気アニメの主題歌などが収録されていることも多く、安価ながらも、その時代を切り取った貴重な文化資料となっています。
6.レコードの大きさに合わせた正しい保管方法や収納術

レコードは非常にデリケートなため、間違った方法で保管すると、盤が変形して再生できなくなったり、貴重なジャケットが傷んだりして、価値を大きく損なうリスクがあります。
正しい知識を身につけ、あなたのレコードを守りましょう。
6-1.レコードのサイズを問わない正しい保管方法
全てのサイズのレコードに共通して、保管の際は以下の8点を実践してください。
・レコードを聴いたあとはクリーニングする
・垂直に立てて保管する
・静電気対策をする
・湿気の少ない環境を作る
・直射日光を避けて保管する
・レコード専用の袋に入れる
・隙間なく詰めて保管する
・定期的にきれいにする
これらの基本を守るだけで、レコードの寿命を格段に延ばすことができます。
レコードの保管方法については以下の記事でさらに詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
関連記事:【徹底解説】レコードの正しい保管方法やおすすめの保管場所
6-2.レコードのサイズ別のおすすめ収納術
レコードのサイズごとに適した収納家具やアイテムを選ぶと、安全な保管と、コレクションの整理しやすさ・見た目の美しさを両立できます。
それぞれのサイズに合った収納方法を取り入れることで、快適なレコードライフを送りましょう。
6-2-1.12インチ盤の収納術
直径約30cmの12インチ盤(LP盤)の収納には、レコードの寸法に合わせて設計された専用のラックやシェルフを使用するのが最適です。
世界中のレコードコレクターに愛用されているのが、IKEAの「KALLAX」です。1マスの内寸がLPジャケットにほぼぴったりで、強度も十分あり、見た目も美しく収納できます。
そのほかにも、DJが使用するような木製のコンテナボックスなども、大量のレコードを機能的に収納するのに適しています。
6-2-2.7インチ盤の収納術
小さな7インチ盤(ドーナツ盤)は、専用の収納ボックスやケースに入れて保管しましょう。
7インチ盤の場合、LP盤と一緒に棚に並べると、重みで曲がってしまったり、見つけにくくなったりします。そのため、7インチレコードがぴったり収まるサイズの、段ボール製や木製、プラスチック製の専用ボックスの利用がおすすめです。
また、アーティスト名のABC順などで整理するための「仕切り板」を活用すると、聴きたい曲をすぐに見つけ出せて便利です。
7.まとめ:レコードの大きさを理解して、アナログの魅力を楽しもう
この記事では、レコードの大きさや回転数といった基本的な規格の違いから、それぞれの正しい再生方法、そして大切なレコードを長持ちさせるための保管方法までをご紹介しました。
レコードには主に、「12インチ盤(LP盤)」「7インチ盤(EP盤/ドーナツ盤)」「10インチ盤」の3つの大きさが存在します。大きさにより再生の仕方が違ったり、収録できる曲数が違ったりするのが、レコード最大の特徴です。
ぜひ、この記事で得た知識を活かして、レコードを手に取り、針を落とし再生する、その一つ一つの所作を楽しんでみてください。
GYOKKODOでは、アナログレコードやCD、DVDなど、音楽関連商品の高価買取を実施中です。ご自宅に不要になったアナログレコードがある方は、GYOKKODOの店頭買取や宅配買取をぜひご利用ください。
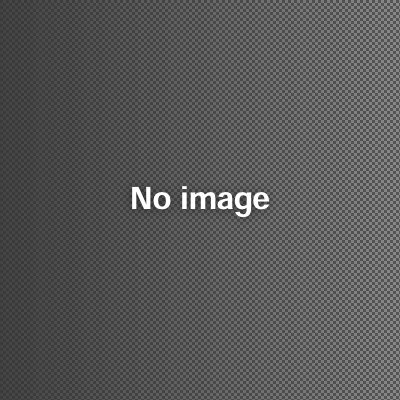
コラム監修者
テキスト〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇