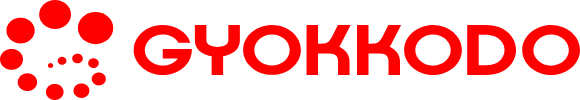2025/05/08
レコードから音が出る仕組みをわかりやすく解説 | 溝や針と音の関係

「レコードって、どうやって音を出しているの?」と疑問に思っていませんか?レコードが好きでよく使っているけど、音が出る仕組みが分からないという方は意外と多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では、以下の内容について解説していきます。
・アナログレコードの構造や素材について
・レコードから音が出る仕組み
・レコードプレイヤーを構成する3つの部品
・レコードプレイヤーの駆動方式
この記事を読むことで、レコードから音が出る仕組みへの理解が深まり、レコードがさらに好きになるきっかけになるでしょう。レコードへの知見を広げるために、ぜひ最後までご覧ください。
目次
1.まずはアナログレコードの構造や素材を知ろう
レコードから音が出る仕組みを解説する前に、まずはアナログレコードの構造や素材を知りましょう。ここでは、アナログレコードの素材や構造について解説していきます。
1-1.アナログレコードの素材は塩化ビニル樹脂
アナログレコードの主な素材は、塩化ビニル樹脂というプラスチックです。これはポリ塩化ビニルとも呼ばれる物質で、普段は硬くて丈夫ですが、熱を加えると柔らかくなり、冷やすとまた硬くなるのが主な特徴です。
熱して柔らかくした塩化ビニル樹脂の円盤に、音の情報を凹凸として溝に刻み込み、冷やして固めるのが基本的な製造方法です。
1-2.レコード盤には溝(音溝)が彫られている
レコード盤の表面には、音楽の情報を記録した「音溝(おんこう)」と呼ばれる細い溝が、中心から外側へ向かって渦巻き状にびっしりと彫られています。この溝の形そのものが、音の波形を物理的に記録したものです。
溝の幅や深さ、そして左右の壁の凹凸が、音の大きさや高低、左右のバランスといった情報をすべて持っています。まるで音の設計図が刻まれているようなものですね。この繊細な溝を正確に読み取ると、豊かなアナログサウンドが再生されるのです。
音溝の形状や刻まれ方は、モノラル盤とステレオ盤で異なります。
1-2-1.ステレオ盤
ステレオ盤は、左右の音を分離して記録するため、立体的な音場を再現できます。
1957年にウエストレックス社が開発した「45-45方式」により、左右のチャンネルの音がそれぞれ45度の角度で溝に刻まれています。これにより、1本のレコード針で左右の音を同時に再生することが可能となりました。
ステレオ盤は、モノラル盤に比べて臨場感や奥行きのある音を楽しむことができ、特にクラシックやジャズなどの音楽でその特徴が顕著です。
1-2-2.モノラル盤
モノラル盤は、単一の音声信号を横方向の振動で記録する方式です。溝の左右両側が同じ形状で刻まれており、レコード針は横方向の動きだけで音を再生します。
モノラル盤は、ステレオ盤に比べて構造がシンプルで、音の芯が太く、力強い音質が特徴です。特に1950年代以前の録音では、モノラル盤が主流であり、当時の音楽を忠実に再現するにはモノラル盤が適しています。
1-3.アナログレコードのサイズ
アナログレコードには、主に3つのサイズが存在します。
最も一般的なのは直径約30cm(12インチ)の「LP盤」です。LPは「Long Play」の略で、片面に20分以上の音楽を収録できるため、アルバム作品によく使われます。
次にポピュラーなのが、直径約17cm(7インチ)の「EP盤」です。「Extended Play」の略ですが、片面に1曲ずつ収録されるシングル盤として広く知られています。中央の穴が大きいものは「ドーナツ盤」とも呼ばれています。
そして3種類目が、直径約25cm(10インチ)の「SP盤」です。これは古い規格のレコードで、LP盤が登場する前は主流でした。現在ではLP盤とEP盤が中心となっています。
2.レコードから音が出る仕組み

ここからは、レコードから音が出る仕組みについて、以下の手順に沿って解説していきます。
1.針がレコード盤の溝に沿って振動する
2.振動がカートリッジで電気信号に変換される
3.アンプによって音が増幅する
それぞれ見ていきましょう。
2-1.針がレコード盤の溝に沿って振動する
レコードから音が出る最初のステップは、レコードプレーヤーの針がレコード盤の溝に刻まれた凹凸を正確になぞり、物理的に振動することです。
針の先端にあるチップと呼ばれる部分が、回転するレコード盤の溝に触れながら進みます。溝には音の波形がそのまま刻まれているため、針はその形に合わせて上下左右に細かく震えます。この振動が、音楽情報の元となるのです。
針のチップに使われる素材も音に影響を与えます。たとえば、硬くて摩耗しにくいダイヤモンド製のチップは、溝の情報をより細かく拾いやすく、クリアで高音質な再生が可能です。一方、サファイア製のチップは比較的安価ですが、ダイヤモンドに比べると摩耗が早くなる傾向があります。
関連記事:【レコードに傷がついた】傷の原因や修復方法・防止法をご紹介
2-2.振動がカートリッジで電気信号に変換される
レコード針が拾った溝の振動は、カートリッジという部品によって電気信号へと変換されます。カートリッジは、針が起こす物理的な動きを、目に見えない電気の流れに変える、いわば小さな発電機のような役割をになっている部品です。
振動が電気信号へと変換がおこなわれると、音楽の情報が電気的な信号として扱えるようになります。
2-3.アンプによって音が増幅する
カートリッジから出力された直後の電気信号は、実は非常に微弱です。そのままでは力が足りず、スピーカーの振動板を動かして音を出すのは難しいのです。
そこでアンプの出番となります。アンプは、この小さな電気信号を受け取り、その波形を保ったまま、何百倍、何千倍にもパワーアップさせる役割を持っています。ちょうど、マイクで拾った小さな声をメガホンで大きくするようなイメージです。
アンプによってしっかり増幅された電気信号がスピーカーに送られると、ようやく私たちが耳にする音楽として再生されるわけです。
3.レコードプレイヤーを構成する3つの部品
レコードプレーヤーは、主に以下3つの部品から成り立っています。
・ターンテーブル
・トーンアーム
・カートリッジ
これらの要素が組み合わさり、レコードプレーヤーはアナログレコードの音を再生します。各部品の選択や調整によって、音質や再生の安定性が大きく変わるため、使用者の好みに合わせたカスタマイズが可能です。
3-1.ターンテーブル
ターンテーブルは、レコード盤を一定の速度で回転させる回転台です。一般的な回転数は、33 1/3rpm(LP盤)、45rpm(EP盤)、78rpm(SP盤)があります。現在の製品では、電動モーターによって駆動されるのが一般的です。
ターンテーブルの安定した回転が、正確な音の再生に不可欠です。
3-2.トーンアーム
トーンアームは、カートリッジを支え、レコード盤の音溝を正確にトレースするためのアームです。トーンアームの設計や素材、長さなどが、音質に影響を与えます。
また、トーンアームのバランス調整や針圧の設定も、再生音の品質に関わる重要な要素です。
3-3.カートリッジ
カートリッジは、レコード針を通じて音溝の振動を検出し、それを電気信号に変換する装置です。カートリッジの性能や種類によって、再生される音の特性が大きく変わります。
カートリッジには、主にMM型(ムービングマグネット)とMC型(ムービングコイル)の2種類があります。
3-3-1.2種類のカートリッジ
MM型カートリッジは、マグネットが動くことで電気信号を生成する方式で、出力が高く、一般的なアンプに直接接続できます。針の交換も比較的容易です。
一方、MC型カートリッジは、コイルが動くことで電気信号を生成する方式で、出力が低いため、昇圧トランスやヘッドアンプが必要になります。MC型は、より繊細で広い周波数特性を持つとされています。
4.レコードプレイヤーの駆動方式

最後に、レコードプレイヤーの駆動方式(ターンテーブルが回る機構・仕組み)について、以下の3種類を解説していきます。
・リムドライブ方式
・ベルトドライブ方式
・ダイレクトドライブ方式
それぞれ見ていきましょう。
4-1.リムドライブ方式
リムドライブ方式は、モーターの回転をゴム製のアイドラー(中間車)を介してターンテーブルの外周に伝える方式です。この構造により、モーターの振動が直接ターンテーブルに伝わりやすくなっているのが特徴です。
ただ、アイドラーの劣化や摩耗により、回転ムラやノイズが発生することも。そのため現在では、リムドライブ方式を採用したプレーヤーはほとんど見られなくなりました。
4-2.ベルトドライブ方式
ベルトドライブ方式は、モーターの回転をゴム製のベルトを介してターンテーブルに伝える方式です。
モーターとターンテーブルが物理的に離れているため、モーターの振動がターンテーブルに伝わりにくく、静かな再生が可能です。また、構造がシンプルで製造コストが低いため、比較的安価なプレーヤーに多く採用されています。
ただし、ベルトの劣化や伸びにより回転数が不安定になることがあるため、定期的なメンテナンスが必要です。
4-3.ダイレクトドライブ方式
ダイレクトドライブ方式は、モーターの回転が直接ターンテーブルに伝わる方式です。この構造により、起動や停止が速く、回転数の安定性が高いのが特徴です。また、トルクが強いため、DJプレイなどでの使用にも適しています。
一方で、モーターの振動が直接ターンテーブルに伝わるため、音質に影響を及ぼす可能性もあります。
5.不要になったアナログレコードはGYOKKODOにお売りください
ご自宅に不要になったアナログレコードがある方は、音楽専門の買取サービスを展開するGYOKKODOにお売りください。
GYOKKODOでは、アナログレコードやCD、DVDなどの音楽関連商品を多く取り扱っており、専門知識をもつスタッフが1点ずつ丁寧に査定いたします。
また、宅配買取と店頭買取の2つの方法があり、特に宅配買取は全国どこからでも送料無料でご利用いただけるため、多くのお客様から好評をいただいています。
「不要なレコードを売ったお金でまた新しくレコードを買いたい」「所有しているレコードを整理したい」などお考えの方は、ぜひGYOKKODOまで。詳細は以下のページをご覧ください。
アナログレコード買取なら全国対応・無料査定のGYOKKODO
6.まとめ
レコードから音が出るまでの仕組み(流れ)は、以下の通りです。
1.針がレコード盤の溝に沿って振動する
2.振動がカートリッジで電気信号に変換される
3.アンプによって音が増幅する
レコードプレイヤーを構成する「ターンテーブル」「トーンアーム」「カートリッジ」の3つがそれぞれ動作することで、レコードから音が出るようになっています。
この記事で解説したレコードの仕組みを正しく知り、その音質や特性への理解を深め、音楽鑑賞の楽しみをさらに広げていきましょう。
GYOKKODOでは、アナログレコードやCD、DVDなど、音楽関連商品の高価買取を実施中です。ご自宅に不要になったアナログレコードがある方は、GYOKKODOの店頭買取や宅配買取をぜひご利用ください。
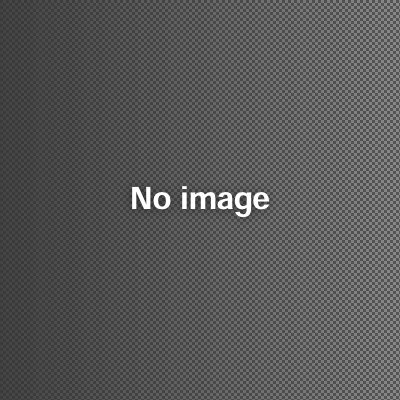
コラム監修者
テキスト〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇