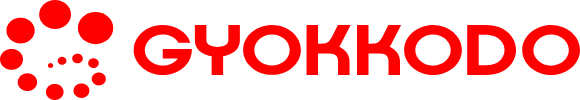2025/08/12
【徹底解説】レコードとは?基本から種類・音の再生に必要なもの

最近、人気が再燃しているアナログレコード。その温かみのある音や、大きなジャケットアートに興味を持たれている方も多いのではないでしょうか。しかし、いざ始めようとすると、「プレーヤー以外に何が必要?」「LP盤とEP盤って何が違うの?」など、分からないことだらけで、最初の一歩をためらってしまいます。
そこでこの記事では、レコード初心者のあなたのために、その仕組みや魅力といった基本から、必要な機材、正しい再生・保管方法まで、アナログライフを始めるための全てを、この記事一本で徹底的にガイドします。
レコードに興味がある方、レコードで音楽を聴いてみたいとお考えの方は、ぜひ参考にしてください。
目次
1.レコードとは?今さら聞けない基本の「き」

レコード(アナログレコード)とは、円盤の表面に刻まれた微細な溝に、音の波を物理的に記録した、音楽メディアの原点ともいえる存在です。デジタルデータではなく、音そのものを「形」として記録しているのが最大の特徴です。
ここからは、レコードで音を再生する仕組みと、レコードの魅力について解説していきます。
1-1.レコードで音を再生する仕組み
レコードは、盤に刻まれた音の溝をレコード針がなぞることで生まれる「振動」を電気信号に変換し、それを増幅してスピーカーから音を出す、という仕組みになっています。具体的には、以下のような流れd音が再生されています。
1.回転するレコードの溝を針が正確にトレースすると、溝の凹凸に応じて針が細かく振動する
2.1の物理的な振動を、針の根本にあるカートリッジという部品が微弱な電気信号に変換する
3.電気信号をアンプでスピーカーを鳴らせるレベルまで大きくし、最終的にスピーカーが電気信号を再び空気の振動、すなわち「音」に変える
この一連の流れ全てがアナログでおこなわれることが、レコードならではのサウンドを生み出します。
関連記事:レコードから音が出る仕組みをわかりやすく解説 | 溝や針と音の関係
1-2.デジタル音源にはない、レコードならではの3つの魅力
現代のデジタル音源にはない、レコードならではの魅力を3つご紹介します。
・温かみのあるサウンド
・アート作品としてのジャケットを所有する喜び
・音楽とじっくり向き合う「手間」と「時間」
それぞれ解説します。
1-2-1.温かみのあるサウンド
レコードの最大の魅力は、その独特な音質にあります。デジタル音源が音を点(0と1)の集合として記録するのに対し、アナログレコードは音の波形をそのまま溝に刻み込みます。そのため、非常に滑らかで、奥行きと温かみのあるサウンドが生まれるのです。
また、理論上は人間の耳に聞こえないとされる高周波数の音も記録されているため、演奏された空間の空気感や、楽器の細やかな響きといった、「情報量の豊かさ」を音から感じられます。
この「アナログならではの音の温かさ」が、多くの音楽ファンを魅了しています。
1-2-2.アート作品としてのジャケットを「所有」する喜び
CDよりも遥かに大きいジャケットは、それ自体がひとつのアート作品です。スマートフォン画面の小さなサムネイル画像とは比べ物にならない迫力で、アーティストが意図したビジュアルを隅々まで楽しむことができます。
歌詞カードやライナーノーツを手に取って読みながら、音楽にじっくりと浸る時間は、レコードならではの体験です。お気に入りの一枚を部屋に飾るなど、音楽を「聴く」だけでなく、フィジカルな「モノ」として所有し、愛でる喜びを与えてくれます。
1-2-3.音楽とじっくり向き合う「手間」と「時間」
レコードを聴くという行為は、デジタル音源のようにワンクリックで完結しません。レコードを袋から丁寧に取り出し、プレーヤーにセットし、そっと針を落とす。片面が終われば、ひっくり返す必要があります。
この一連の「手間」のかかる儀式的な時間は、音楽とじっくり向き合うための大切な準備時間となります。簡単に曲をスキップできないため、アーティストが意図した曲順でアルバム一枚を集中して聴くことになり、ストリーミングでは気づかなかった曲の魅力や、アルバム全体のストーリー性を発見できます。
この「不便益」こそが、音楽への没入感を高めるのです。
2.なぜ今、再びレコードがブームになっているのか?
今、若者を中心にレコードがブームになっているのをご存じですか?
昭和の時代に流行したレコードが、音の温かみやジャケットのアート、音楽との向き合い方としての価値が評価され、再燃しているのです。2024年、レコードの生産額は35年ぶりに70億円を超え、アイドルやJ-POPアーティストが新譜をレコードで発売するなど、需要が拡大しました。
上記は、デジタル音源では味わえない「モノとしての価値」が注目された結果です。若者はインテリアとしてもレコードを楽しみ、音楽と向き合う新しい形が広がっています。
参考:若者がハマる「モノとしての価値」レコードブーム再燃の謎、生産額35年ぶり70億円突破の理由(FNNプライムオンライン) – Yahoo!ニュース
レコードブームについては、以下の記事でさらに詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
レコードブームが起きている4つの理由!若者を惹きつけるレコードの魅力
3.レコードの主な種類とそれぞれの違い

レコードは、主に大きさや回転数によって以下3つの種類に分類されます。
・LP盤(12インチ)
・EP盤(7インチ/ドーナツ盤)
・SP盤
それぞれの違いを見ていきましょう。
3-1.LP盤(12インチ)
LP盤は、直径約30cm(12インチ)の大きさで、アルバム作品を収録するために作られた、最も標準的なレコードです。LPは「Long Play」の略で、その名の通り、片面に20分以上の長時間収録を可能にしています。
33 1/3回転(33rpm)で再生され、アーティストが表現したいアルバム全体の流れや世界観を、A面・B面通してじっくりと楽しめるのが最大の魅力です。
一般的に「レコード」と聞いて多くの人が思い浮かべるのが、このLP盤です。
3-2.EP盤(7インチ/ドーナツ盤)
EP盤は、直径約18cm(7インチ)のコンパクトなレコードで、主にシングル曲を収録するために使われます。中心部の穴が大きい見た目から、「ドーナツ盤」とも呼ばれます。
EPは「Extended Play」の略ですが、片面に1〜2曲を収録するのが一般的です。再生速度は45回転が主流で、LP盤よりも高音質で迫力のあるサウンドを記録できるという利点もあります。
関連記事:「EP」の意味とは?定義やシングル・アルバムとの違いについて
3-3.SP盤
SP盤は、LP盤が誕生する以前の1950年代まで主流だった、1分間に78回転で再生する古い規格のレコードです。
SPは「Standard Play」の略で、シェラックという樹脂を主原料としているため、重くて割れやすいのが特徴です。収録時間も片面3分程度と短くなっています。
また、音を記録する溝の幅がLP盤とは全く違うため、再生には専用の針(SP盤用カートリッジ)が必須です。
関連記事:SPレコードとは?特徴や歴史・再生方法・LP盤との違いなど徹底解説
4.レコードを聴くために準備するもの
レコードを再生したい、聴きたいとお考えの方は、レコード以外に以下3つのアイテムを用意してください。
・レコードプレーヤー
・アンプ(フォノイコライザー)
・スピーカーまたはヘッドホン
それぞれ解説します。
4-1.レコードプレーヤー
レコードプレーヤーは、レコード盤を回転させ、針で溝に記録された情報を読み取る、アナログ再生の心臓部となる機材です。
レコードプレーヤーを選ぶ際は、再生したいレコードの回転数(33/45/78回転)に対応しているかを確認する必要があります。また、トーンアームやカートリッジといった部品の品質も、音質に大きく影響します。
近年では、USB端子を備え、レコードの音をデジタル音源としてパソコンに取り込めるモデルも人気です。
4-2.アンプ(フォノイコライザー)
アンプは、レコードプレーヤーから送られてきた微弱な電気信号を、スピーカーを駆動できるレベルまで増幅(アンプリファイ)する役割を担います。
とくに、レコード再生には「フォノイコライザー」という専用の回路が不可欠です。これは、レコードに記録する際に加工された音を、元のバランスに戻すためのものです。
アンプに「PHONO(フォノ)入力」端子があれば、この回路が内蔵されています。もしPHONO入力がないアンプの場合は、別途単体のフォノイコライザーを接続する必要があります。
4-3.スピーカーまたはヘッドホン
スピーカーやヘッドホンは、アンプで増幅された電気信号を、最終的に我々が耳で聴くことができる「音」という空気の振動に変換する、音の出口です。
スピーカーは、部屋全体に広がる豊かなサウンドを楽しめるのが魅力です。一方、ヘッドホンは、夜間でも大音量で楽しめたり、レコードの細やかな音の粒まで集中して聴き込んだりするのに適しています。
レコードの温かみのあるサウンドを、最終的にどんな音色で楽しみたいか、好みに合わせて選ぶと良いでしょう。
5.レコードの正しい再生方法と取り扱い方

大切なレコードを長く楽しむためには、再生前の準備から、針の上げ下ろし、そして再生後の手入れまで、一連の正しい取り扱い方をマスターすることが大切です。
デリケートなレコード盤と針は、少しの油断で傷がついてしまうことがあります。これからご紹介する手順を習慣づけ、あなたのレコードコレクションを良い音で楽しみましょう。
5-1.レコード再生前の準備:回転数とEPアダプターの確認
レコードをプレーヤーにセットしたら、まず盤の規格に合わせてプレーヤーの回転数(基本的には33か45)を正しく設定しましょう。その際、7インチ盤の場合はEPアダプターを装着してください。
最初のセットを怠ると、音楽が正しい速さで再生されなかったり、7インチ盤が中心からずれて正常に再生できなかったりします。正しい音で再生するためにも、レコード盤の回転数を必ず確認しましょう。
5-2.針を落とす際の注意点
レコードに針を落とす際は、トーンアームのリフター(アームを上げ下げするレバー)を使い、ゆっくりと慎重におこなうのが、レコードと針を傷つけないための重要なコツです。
手で直接アームを持って針を落とそうとすると、勢い余って盤面に針を落としてしまい、レコードに深い傷を作る原因となります。リフターを使えば、誰でも安全に、狙った曲の頭に優しく針を落とすことが可能です。丁寧に操作することで、ノイズの原因となる傷を防ぎ、大切なレコードを守ります。
5-3.再生後のお手入れ
レコードを聴き終えたあとは、盤面のホコリや静電気を除去するために、専用のレコードクリーナーやブラシで軽く清掃するのが理想的です。レコードの溝にたまったホコリは、再生時のノイズの原因になるだけでなく、針先を傷めることにも繋がるためです。
再生によって発生した静電気も、新たなホコリを引き寄せてしまいます。毎回のお手入れを習慣にすると、いつでもクリアな音質を保つことができるのです。
5-4.レコードの正しい保管方法
レコードを保管する際は、盤の反りを防ぐために必ず「立てて」置き、熱、湿気、そして直射日光を避けるのが、全てのレコードに共通する鉄則です。
レコードを平積みすると、自らの重みで歪んでしまい、再生不可能になることがあります。また、高温は盤の変形、湿気はジャケットのカビ、直射日光は色褪せの直接的な原因となります。
風通しの良い、涼しい日陰で、本のように立てて保管することを心がけてください。
6.レコードを購入できる場所

レコードは、品揃え豊富な「中古レコード店」や、新品を扱う「CDショップ」、そして手軽な「オンラインストア」など、様々な場所で購入できます。それぞれにメリット・デメリットがあるため、あなたが探しているレコードの種類や、買い物のスタイルに合わせて、利用する場所を選ぶのがおすすめです。
6-1.中古レコード店
中古レコード店や専門店は、膨大な在庫の中から、宝探しのように思いがけない一枚に出会えるのが最大の魅力です。廃盤になった昔のレコードや、珍しい限定盤などを見つけることができます。
知識豊富な店員さんに、おすすめのアーティストやジャンルについて相談できるのも、専門店ならではの楽しさです。盤の状態を自分の目で直接確認して購入できるという安心感もあります。
6-2.新品を扱うCDショップ
タワーレコードやHMVなど大手のCDショップでは、新品のレコードを購入できます。現在活躍している人気アーティストの新作や、過去の名盤の「リイシュー(再発)盤」などを中心に販売されています。
新品なので、盤の状態を心配する必要がなく、誰でも安心して購入できるのが大きなメリットです。ポイントカードなどが使える場合は、お得に買い物をすることもできます。
6-3.オンラインストア・フリマアプリ
Amazonなどの大手ECサイトや、前述したようなCDショップのオンラインストア、そしてフリマアプリは、自宅にいながら世界中のレコードを探すことが可能です。
実店舗では見つからないような、海外の珍しいレコードや、個人が出品する安価なレコードを見つけられる可能性があります。ただし、盤の状態を直接確認できないため、出品者の評価をよく確認するなど、慎重な判断が必要です。
豊富な品揃えと利便性が、オンライン購入の大きな魅力といえるでしょう。
7.まとめ
この記事では、レコードの基本的な仕組みから、種類や聴き方、そして保管方法まで、レコードを始めるために必要な知識を網羅的にご紹介しました。
レコードの再生は、デジタル音源に比べると少し手間がかかるように感じるかもしれません。しかし、お気に入りの一枚を探し、プレーヤーにセットし、針をそっと落とす、その一連の時間こそが、音楽と深く向き合う豊かな体験を生み出してくれます。
この記事で解説した内容を参考に、お気に入りの一枚を探してみてください。
GYOKKODOでは、アナログレコードやCD、DVDなど、音楽関連商品の高価買取を実施中です。ご自宅に不要になったアナログレコードがある方は、GYOKKODOの店頭買取や宅配買取をぜひご利用ください。
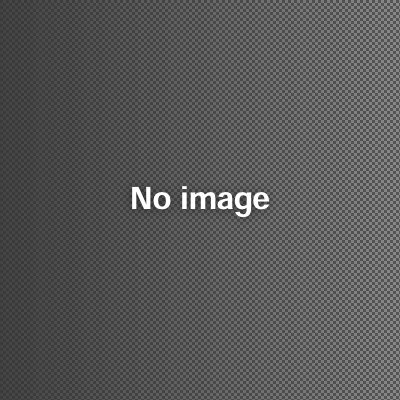
コラム監修者
テキスト〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇